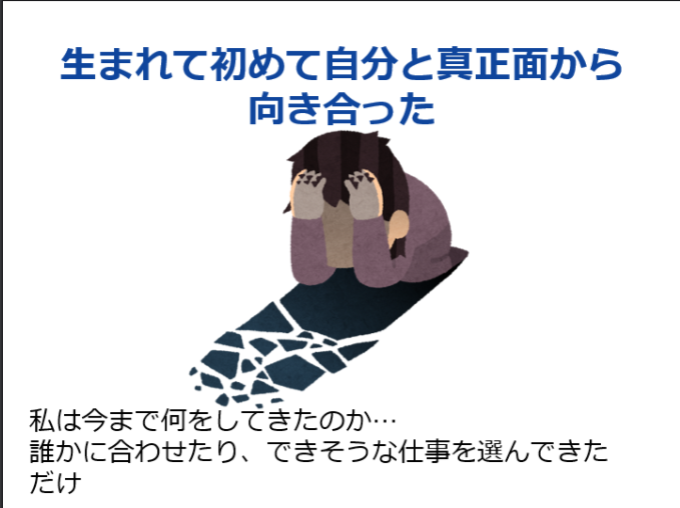どーも。みやこ(fa50420)です。
肩書が複数ある自営業なので、職業を訊かれたときはその場に合わせて最適なものを答えているのですが、最近はキャリア教育コーディネーターと答えることも多くなってきました。
じゃあキャリア教育コーディネーターってなんなのよ、ってなると思うんですが、『子どもたちが自分らしい生き方を見いだせるよう、地域社会と学校を結びつけてキャリア教育の支援を行っています』と答えています。
この辺はまた別の記事で書くと思うのでひとまずさておいて、今月は各地でキャリア教育支援活動をしてきました。どんなことをしてきたのか、ご報告したいと思います。
高校生のキャリア授業で話をしてきた
いつもお世話になっている教育系NPO団体さんから、今まで行ってきたキャリア授業プログラムを発展させたいのでテストケースになって欲しいという依頼があり、行ってきました。
TEDのプレゼンテーションがイメージに近いのですが、1人の社会人が30分程度テーマに沿った話を高校生相手にプレゼンテーションしていきます。
実際にプレゼンするときよりも、テーマを頂いてから具体的な話をヒアリングされたときが個人的には一番大変でした。
というのは、今回のテーマが「仕事で壁にぶち当たったとき」ですので、今まであまり他人に話してこなかった苦しい経験を自分の言葉で語らなければならないうえ、無意識に記憶に蓋をしてしまっているのか「一番悔しかったポイント」や「その時どう思ったのか」などが尋ねられたその場ではすぐに言葉になりませんでした。
ヒアリングで深掘りされたことを改めて考えながらスライドのプロットを作っていくと、いつの間にか記憶が蘇って臨場感あふれるスライドが作れました。
もしヒアリング無しにプレゼンを作っていたら、表面的で誰の心にも響かないものになっていたかもしれません。
キャリア授業というと「すごい経歴のある大人がやってきて、説教じみた話をする」というのは今もほとんど変わらないらしく、とてももったいないことだと思います。
誰かの自慢話やお説教が始まるって思うだけで逃げ出したくなるけど、授業だというと逃げられないですからねぇ。話が始まれば生徒は話の内容なんて上の空になって寝ちゃうし、せっかく話に来た大人は怒り出すしでどちらにとっても良くないです。
こちらのNPOさんでは、「キャリア授業=つまらない」の公式を変えようとされていて、バラエティ番組のように生徒を飽きさせないプログラムになっています。
プレゼンター入場時に芸能人のモノマネをしたり(これはプレゼンよりも練習しました笑)、生徒たちと一緒になってゲームをしたり。
「場」をあたためて、生徒と大人の距離感が縮まったところでプレゼンが始まります。
3人のプレゼンターのうち私がトップバッターだったのですが、話の最初こそ机に伏せった子もいたけれど段々と真剣な顔つきで聴きいってくれたのには感動しました。
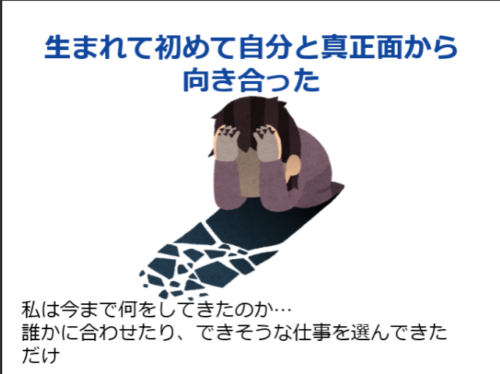
スライドの一部。
話し終わったあと生徒たちから質問の手がたくさん挙がったのも嬉しかったです。生徒の聴きたかった答えになっていたかはわかりませんが、自分が普段考えていることや大事にしていることは伝えられたと思います。
プレゼンター全員の話を聴き終えて、生徒たちが感想を共有する時間も良かったです。
集められた生徒は学校や偏差値も違っているうえ、今回はテストケースなので大学生も混じっていたのですが、それぞれが自分の考えを表現できていたし感想もそれぞれで興味深かったです。
プログラム終了後、「とても良いお話だったので、いろんな場所でお話してください!」と直接大学生の子に言われました。
この授業のお話をいただくまで「嫌な記憶」になっていたことが、社会に出る前の子たちにとっては役立つ経験になっていたのかな、と思うとプレゼンしてよかったなーと思います。
そうだね、失敗や困難をその後の人生の糧にできる人を大人って呼ぶのかもしれないね。
高校生たちが社会経験を積む「場」を繋いできた
農業高校の生徒たちが出店・販売したり、学校活動の発表ができる「場」として、地元のイベントをつなげてきました。
実際のところ、この学校では生徒があちこちに出向いて発表しているので場数を踏んでいるためか、しっかりした考えを持っている子が多い印象があります。
でも、今度紹介したのは「赤ちゃん〜幼児を持つ母親向けイベント」なので、発表内容や販売時の対応も文化祭や学生カンファレンスとはアピールの仕方が変わってきます。そのため、具体的なイベント内容や生徒たちにやってほしいことをオリエンテーションしてきました。
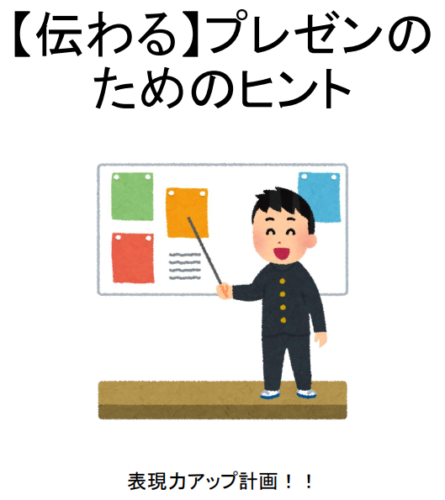
ヒント集の表紙
私は『どんなプレゼンが相手に伝わるか』といったことを、簡単なヒント集を作って生徒たちに話してきました。
プレゼンヒント集と題しながらも表現方法全般についての内容なので、販売のPOPや学校のレポートなどに活用してくれたら嬉しいな。
イベントでは「おもてなし」を大切にしているので挨拶の練習や、パンフレットに掲載するインタビューも同時に行ったため、生徒たちも大変だったと思いますが、ニコニコしている子が多くてイベントを楽しみにしているように感じられました。

お辞儀をするときは自分がコンパスになったつもりで。
開催日は来月ですが、私たちも彼らに最高の「場」を用意してあげたいと思っています。
出前授業で高校1年生と対話してきた
「来週、高校へ出前授業するんですけどご一緒できませんかー?」
群馬県を活動フィールドにしているNPOの方から、こんなメッセージが飛び込んできたので、「いいよー!」と即答していました。
絶対楽しいってわかってたんで!
私のキャリア教育の師匠から学んだ方たちが運営しているNPO団体です。いわば兄弟弟子で、仲良くさせてもらっています。
20代や大学生中心の団体ですがキャリア教育活動は長くやっていらっしゃるので、一緒に活動するたびに学ばせてもらっています。
出前授業する高校まで約2時間、高速道路を飛ばしてやってきました!
今回の授業で私の役目は、「今までの自分」と「これからの自分」を書き出すワークのサポート役の一人。
高校1年生ぐらいだとまだまだ思考力や表現力に幼さが残る子もいるので、対話しながら引き出してあげる役割です。
高校に入学して2ヶ月近く経ち、学校と馴染んできた時期にこういったワークをする理由は、3年間を充実して過ごしてほしいから。
ダラダラ流されて過ごすもチャレンジして過ごすも同じ3年間。大人とも子どもとも違う高校生活の過ごし方を、ちょっと立ち止まって考える時間にしてほしい出前授業です。

15分区切りで2,3人相手に3回転。ワークシートにスラスラ記入する子もいれば、考え込んでしまう子も。
考え込んでしまう子には、シートに記入された回答を元に突っ込んで聴いていきます。
「この将来の夢面白いね! なんでこんな風に思ったの?」
キャリア教育の支援活動をしていて何より楽しいのは、私よりずっと年下の世代が普段考えていることに直接触れられること。
私が本気で高校生目線になって楽しんでいることが分かるから、相手も本音を出してくれるんだと思っています。
もっと大人数相手のグループワークをファシリテーションしたことはありますが、対話の時間や内容に物足りなさを感じていたので、今回の人数や時間はちょうどよく感じました。
この授業の締めくくりは、シートに書き出した「1学期が終わるまでにやりたいこと」など目標や夢をグループ内で発表すること。
この年頃の子たちにとって、同級生たちに将来の夢を発表するというのはじつはちょっとしたハードルです。
からかわれたりしないか批判されないかドキドキした子もいたと思いますが、相手の考えを尊重する雰囲気づくりも私たちの役目。
無事、全員が発表することができました。
授業終了後、感想を共有してみると「2時間じゃできることが少なくて……」という意見が多く聞かれました。
でも、教育って成果がすぐ出るものではないし出ても分かりにくいものなんです。そこがビジネスとは違うし、そこを楽しめるような心構えでいることが大切なのかも。
そして、私たちが些細な関わりだと思っていることが、生徒たちの内面に大きな変化をもたらしていることもあるんです。良い変化であれ、悪い変化であれ。だからこそ、ときには失敗や挫折もする一人の人間として、生徒に本音で向き合うということが大切だと考えています。
ほんっと、キャリア教育支援活動は楽しいし、たくさんの人に関わってほしいなって思ってます!!☆-(ノ゚∀゚)八(゚∀゚ )ノイエーイ☆